全年全月28日の投稿[6件]
2024年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
#サン星
「星さん?あの、これは一体」
「友達――アベンチュリン――から貰ったの。だから、あなたにあげる」
「あげると言われましてもこれはまた大金ですよ」
「そうだね。だから、あなたが使って」
「どうしてです?」
「いつも投資話をおじゃんにするじゃない!私はお金を出すと言っているのに」
「あなたは良くてもあなたの保護者達に何を言われるかと思うと僕のリスクが高いんですよ」
「じゃあなんでいつも声をかけてくるの?」
「あなたが簡単に乗るからですよ」
「矛盾?」
「楽しいからいいじゃありませんか」
「まあ、それは……そう。だから、私が投資話を作った」
「だから?」
「だから」
「一から話してください」
「十から話したのに?」
「それが問題なんですよ」
「私、お金貰う。サンポ、そのお金を使う。終わり」
「あなたの話術を指南する本を作ると売れそうですね」
「じゃあ、このお金で作ろう!」
「ゼロから話すのはどうでしょう?」
「回りくどいな。いいから使えと言ってるんだけど」
「正直に言うと恐ろしさを覚えています。わけもわからず他人……いえ、ごほん。親愛なる友人の星さんからお金を使えと言われて。まったく混乱してしまいます。これは罠かなにかでしょうか?」
「シンプルに話してるんだけどな」
「シンプル……というか、マッチを使って火をおこすのではなく、雨を降らせろと言われているような気分なのですが」
「じゃあそれをしよう。このお金で」
「すみません、壊れたカセットテープよりも異常な停止と繰り返しを行わないでください」
「私を失望させないで」
星が言う。
サンポは目を細めた。
「私めに何をさせたいのですか。私めは商人ですから、事は単純なのです。お客様の欲しいモノを買う。お客様の欲しいモノを売る。それだけなのですよ。」
「サンポがこのお金でサンポの欲しいものを買ってきて、私を満足させる。以上」
「僕の欲しいものでどうして星さんが満足されるのですか?」
「サンポの欲しいものが見たいから。」
「おやまあ、……いえちょっと待ってください。一体どうされたのですか?ゴミ箱に脅迫されているんですか?どのあたりの?まさかこの前一緒に穴を掘っていたあれですか?」
「どの話?心当たりが多くて分からない」
「はあ」
サンポがため息を吐いた。
星はてへへと照れたように頭を掻いた。
「じゃあそういうことで」
「待って。待ってください。僕、何かあなたを怒らせるようなことをしましたか?」
「存在がもう………あれは許せなかったな………」
「えぇえ……償いならもうしたじゃないですかぁ、ってどのことですか?心当たりがまるでないのですが……」
「サンポじゃなかったからね。でもサンポの顏してたからそういう時はサンポが悪いよ」
「―――ということは、つまり」
「てへへ」
「八つ当たりじゃないですか?サンドバックの代金ということですかぁ?」
「願いは本当。怒りも本当だよ。いや、正当かな……大体サンポが悪いじゃん……」
「あのー。まったく理不尽さを覚えるのですが、はあ、もう分かりましたよ。ならそういうこととして、お金は預からせていただきます。……僕の欲しいもの、でしたよね?」
「まあ犬のうんこみたいなもんだと思うけどね」
「今ふかーく傷つきましたよ。本当ですからね、ああ、悲しい……良き友、良き仲間、良き同士、こうして時間をかけてお互いを知り合い、深くつながった関係だと言うのに……星さんはまったく僕のことをお分かりになっていないなんて!この不肖サンポ、悲しすぎてもう涙も枯れはててしまいました」
「乙~。じゃあ、楽しみにしてるね」
「あ、ちょっと!」
星は本当にさっさと歩きだして、街灯に喧嘩を売りに行った。街灯の方はまったく気にせず、そびえたっている。むしろその近くにあるポストの方が彼女のことを気にしているようだ。この街は終わりだ。
「……さてと」
本当に大金だった。彼女からして、だが。それをささーっと懐にしまい込み、サンポもまたその場を去ることにした。自分の欲しいものはお金では買えない。大事なものはお金で買えないのだ。まあ、大抵の場合だが。何があったのか、おおよその見当はついているものの、かといって自分の所為ではないことは確かだ。八つ当たりの代金は頂くとして、彼女の願いを叶えないといけない。売られて、買ったのだ。このサンポ、いついかなる時もお客様を失望させるようなことは致しません。決して差し出すのは、犬のうんこなどではないのだ。……………彼女は、結構喜びそうだ。物語はそうやって破綻した。パーン。終わり。
#冠特
寝ている。呼び出したのは自分だ、部屋で待っていろと言ったのも自分だ。
彼は煙草を手に取り、火を点けた。浅く吸い込み溜めてから吐き出す。
ちろりと詰みあがっている書類を見る。見るだけだ。
机に腰を下ろし、人のソファで間抜けに眠りこけている彼女を見る。
煙草を吸う。吐く。二本目に火を点けた。紫煙が漂う。
彼は特に何も考えていなかった。どうでもよかった。
彼女は眠っている。
二本目を吸い終えたら、動くつもりだった。
が。先に腹の音が鳴った。
彼のものではない。
眠りこけている彼女の腹からだ。
グゥウウーー
勢いよく飛び起きた彼女は彼を見て、不思議そうな顔をし、やがて状況を把握し、青ざめた。腹が鳴り続ける。顔を赤くし、冷や汗を流し、困り果てた顔で、彼女は滑稽なほどにうろたえた。
「あ、えっと、あの、これはその、ええと、だから」
「だから?」
「えっ」
「何だ」
「…………すみません………」
絞り出した声で謝罪し、彼女は死刑を待つ囚人のように項垂れた。
腹は鳴っている。
「御託はいい。消えろ」
「はい、あの、本当にすみませ」
「やる」
「…………あ、え?」
「あ?」
「……えっと」
彼女は瞬いた。
彼が放り投げたのはチョコレートの缶だった。
「押し付けられた。お前が全部食え」
「あ、………えっと…………じゃあ、責任持って食べます、ので」
「ああ」
「失礼しました」
「食えって言ったよな?」
彼女は最大級に間抜けな顔をした。
「……それはその。……ここで?」
彼は答えなかった。
彼女は哀れな子ネズミだった。
何かをすがるように視線を彷徨わせ、やがて決心した。
「いただきます…………」
恐る恐ると彼女はチョコレートを一粒口に含んだ。
「……ん、……あ!美味しい!」
「そうかよ」
「美味しいですよ、冠氷さんも食べませんか?」
「いらねえ」
「美味しいですよ」
「お前が全部食えつってんだろ」
「……誰かからの贈り物ですか?」
「知らねえ」
「こんな美味しいチョコレート、私食べたことないです!」
「で?」
「………………すみません。あの、ここで全部食べなきゃだめですか?」
目線だけ向けた。
彼女は臆病に首を竦める。
「………友達に、あげたくて」
美味しいので、ともごもご言った。
大方、二年の同級生にだろう。
「あ」
「え」
「……」
彼は口を開けて見せた。
彼女が固まった。
「早くしろ」
「えっと……失礼します」
彼女はおずおずとチョコレートを一粒、彼に差し出した。
彼は彼女がそれを口に入れるまで傲然と待った。
彼女は彼の意図に気づき、怯える子羊のまま、王の口に含ませた。
彼は彼女の指ごと、チョコレートを食み、溶かした。
「まあまあだな」
「…………は、はい」
「はい?」
「お、美味しいと思います……」
彼は手を振った。
下がれという意味だった。
部屋から出ていけとも言った。
彼女はわたわたと慌て、チョコレートの缶をしっかりと抱いた。
「あの、冠氷さん、有難うございます」
彼は応じなかった。
彼女はそっと出ていく。
入れ替わるようにして、副寮長が訪れた。
彼はソファに横になり、目を瞑った。
何か色々と言っていたがどうでもよかった。
「おや、チョコレートはどうされたんですか」
不意に含み笑いが聞こえる。
わざとらしい言い回しに彼はいつもうんざりしている。
「失せろ」
「また、用意しておきます。ああ、そうだ」
今度は彼女を呼んで、お茶会をしましょう。
戯言が聞こえる。
彼は沈黙を欲した。
まだ何か話している。
うるさい。
彼の、口の中はチョコレートの味がした。
彼女の爪の硬さが歯に残っている。
その時、一瞬、目が合っていた。
彼は捕食者の顔をしていたし、彼女は無垢な生贄だった。
「美味いやつにしろ」
彼はそれきり、何も話さなかった。
副寮長は従順に承諾する。
彼女は、彼の特別だった。
2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
アナウンス
※現在プレイを休止しているものあります。
倉庫としておいています。
受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり
R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。
年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。
倉庫としておいています。
受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり
R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。
年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。

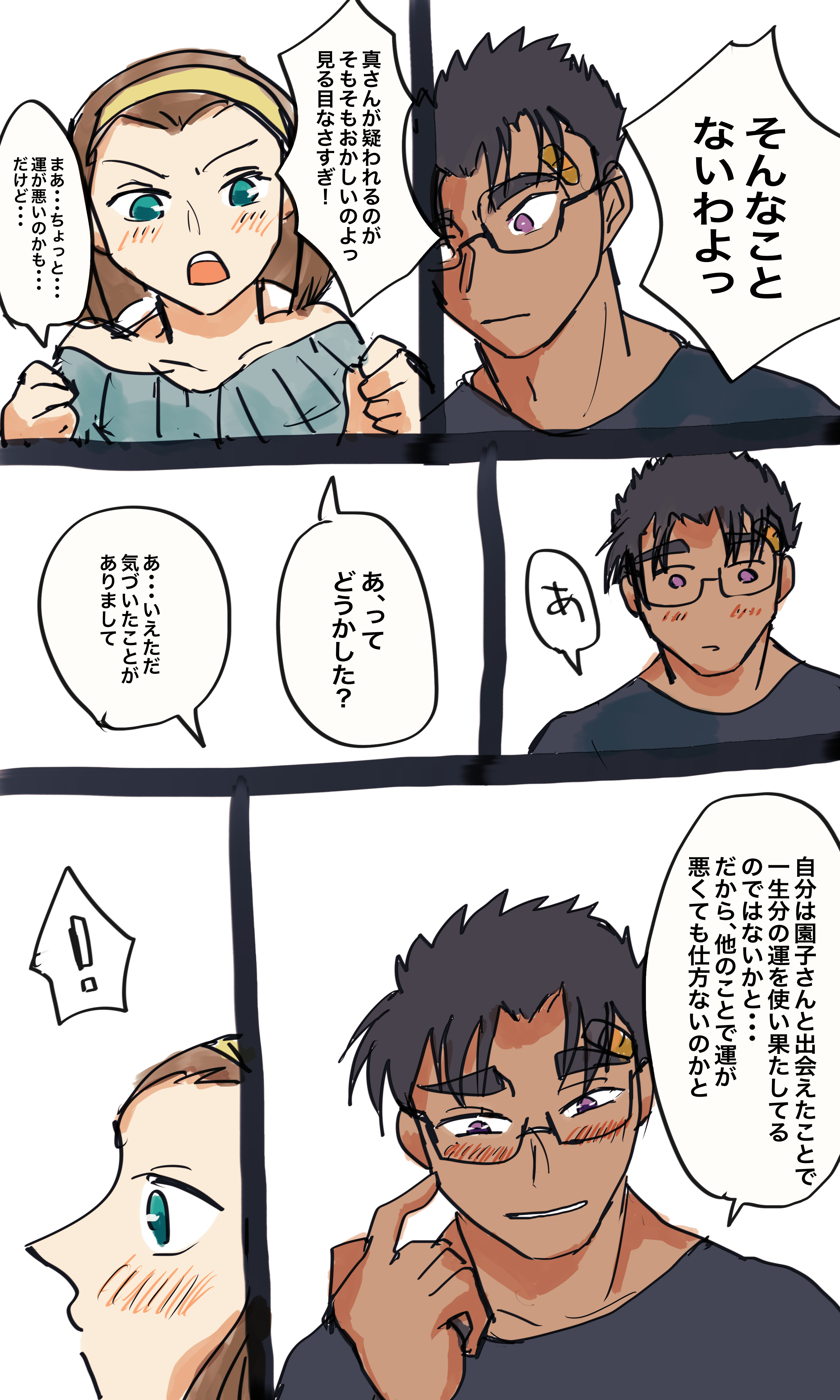








大抵の地球のおかずよりも遥かに良いものたちがここにはあり、何故ならここは地獄だからだ。
天使たちの襲撃が今日は休みで、ここの神も休日を作ったのかもしれなかった。案外常識を持ち合わせたピョンがお出かけになられてはいかがですかと言う、ゲヘナはとても素晴らしい街ですよ、と言う。襲撃の後に朽ち果てた建物があっても活気に満ちていて、美しかった。一人で行ってもいいものかと確認する前に、ちょうどいい、とピョンが言った。ザガンがいた。ザガンは私と目を合わせなかった。そこが気に入った。ピョンに一緒に出掛けてくるといい、はい、それがよろしいですよ、と言い、何か忙しそうに出かけて行った。見慣れた赤い丸が、星のように過ぎ去って、無言を決め込むザガンの腕を取った。びくりと驚いて、ザガンは目の端を赤く染めた。
「あなたはどうしてここに?」
「…………」
ザガンはひどく無口で、私は自分の都合よく解釈することにした。
ぴったりとくっつくと熱い皮膚が感じ取れた。シトリーでもなくても鼓動は聞き取れる。
「ゲヘナはいい街だね」
ザガンは頷いた。
「それで、二人きりになれる場所は知っている?」
ザガンは目を丸くした。
私を見て、喉をこくりと鳴らす。
正直で可愛い反応に私は満足した。
「嘘だよ、好きな場所に連れて行って」
ザガンは困ったように眉を下げた。
「どちらがいい?」
ザガンは、顔をそらした。
私は辛抱強く待つことにした。嘘だった。彼の手を握り、彼の腕を触った。
ザガンは首から赤くなって、小さく唸る。
「…………どこがいいのか、分からない」
「酒場があるんだったら宿があるんじゃないかな」
「!」
ここは地獄だったし、彼は悪魔だった
ザガンは私の腕を取ると、真っ直ぐに歩いて行った。私は素直に付き従った。彼が何か他の悪魔に断りを入れ、私は宿の一室に連れてこられる。ザガンの息はすでに荒くて、硬くなって主張していた。
「……キスはしてくれないの?」
ザガンは応じた。
最初は戸惑いがちに、徐々に大胆に。私は受け入れて、ザガンも私を受け入れるころにはお互い裸になっていて、私は彼の均等に鍛えられた美しい身体を目と指で堪能した。唇でも、舌でも。ザガンはベッドにうつ伏せになって、時々唸り、私に許しを請うような目をした。きらきらの犬みたいな、それでいて、あまりにも真っ直ぐだから返って虐めたくなるような目で。
私は彼のものを太ももで挟んだ。
「いれたい?」
「………ああ」
「どうしても?」
「……どうしても」
「どうして?」
「……どうして?」
「言って」
何を、と彼は聞かなかった。
「お前が欲しい」
私は返事をせずに、彼を導いた。
彼はそれだけで震えて、達しそうになった。
好きに動いていい、と言うように私は彼の首を抱き、彼は動き始めた。
動けば動くほどみっちりと質量を増してゆく。
ここは地獄で、地球では中が満ちることはなかった、こんなにも。
彼の髪もとてもいい匂いがして、悪魔はどうしたって魅力的だ。しとどに濡れていく自分も、彼のものも感じて、でも彼は私を壊すわけではなかったし、私も彼に壊されたいわけではなかった。
丁度いい興奮と快楽に、どこか素朴な彼のうっとりとした恍惚した眼差しが気持ちよかった。
「はぁ、はぁ、……気持ちいい?」
「……ああ」
彼はそれに興奮したように、腰の動きを早めていく。乳房を舐めて、先端を吸う。
前にした動きを覚えているようだった。
私の内側も唸っていく。
彼の汗が私に落ちる。
髪を掻き上げて、角を触ると彼は眉をしかめた。
困っているのに、もっと、と強請るようだった。
私は嬉しくなって、彼の角を握る。
彼の動きに合わせてぎゅ、ぎゅ、と動かすと、彼は声を漏らした。
「イキたい?」
「……ああ」
「可愛い」
また彼は困惑して、でもそれをどこか楽しんでるようにして小さく笑った。
私はあとは彼に任せることにして、彼の齎すものを楽しんだ。
美しい男が犬みたいに懐いてくれるのは、心地よかった。
ザガンの余力を残して行為は終わった。甘く痺れて余韻が残っている。私はまだ出来るような気がして、彼の胸元を触った。ザガンは、私の首筋に唇を寄せる。
「今日は終わりだ」
「どうして?」
「お前が疲れているから」
「もっとできるかもしれないでしょう」
「……なら、今度」
今日よりもっとする、とザガンは小さく笑った。
私をあやすように。
「休んでくれ。連れていく」
どこに?
地獄はここだ。
ザガンは私にキスをした。甘い色の眼差しは欲を残していて、そういえばこういうジュースがあった。よく混ぜないと最後に甘い蜜が残ってしまうもの。水を足して飲んでもいいんだけれどそうすると水っぽくなって台無しになってしまう。私は彼の唇を舐めて、彼は、小さく唸った。犬みたいにして。見えない尻尾を振って、私の胸元に頭を寄せた。案外ふわふわとした髪が私の肌をくすぐり、ゆったりとした重みは私を睡眠へ促す。
「また会いたい」
どうしてそんな当然のことを?私は眠気に囚われて、うまく答えられなかったけれど、窓から差し込む光は薄っすらと分かり、それが一層ザガンを美しく見せ、私はゲヘナは素晴らしい街だと、改めて思った。
畳む