2024年1月の投稿(時系列順)[14件]
2024年1月8日 この範囲を新しい順で読む この範囲をファイルに出力する
2024年1月9日 この範囲を新しい順で読む この範囲をファイルに出力する
#京園 /お願い
「真さん、今から思ったことは全部口に出して」
唐突な命令、いえお願いだった。京極真は、ゆっくりと瞬いて、その言葉の意味を咀嚼しようと試みた。
「……つまり、どういうことですか?」
「お腹が空いたなーと思ったら、お腹空いたなーって言ったり、喉が渇いたなーと思ったら喉が渇いたなーって言うの」
「なるほど」
「私が好きだなーと思ったら好きだなーって言うのよ」
「えっ」
「なぁに?不満なの?」
上目遣いで睨まれて、京極真は咄嗟に浮かんだ言葉を打ち消した。
じっと彼女が見つめている。
彼女のお願いであれば出来ることなら叶えるつもりだ。
出来ないことでも叶えられるように精進するつもりだ。
つもりではいけない。
そうする、と決めている。
決めているのだが、京極真は困った顔をした。
「もう、真さん、困ってるなら困ったなーって言うのよ」
「ええと、これはどういう意図での行為なのですか」
「だって普段から真さんが何考えてるのか、気になるじゃない」
京極真は思考を無にした。
思わなければ、何も言わなければ、嘘ではなくなる。
すっと息を吸った。
無我の境地へ至ろうとする京極真を、彼女がゆさゆさと揺らす。
「ちょっとちょっと!いきなり修行モードに入ってない!?」
「そ、そんなことは」
「嘘。絶対そう。どうせ、何も考えないようにすれば何も言わなくていいと思ったんでしょ」
「…………はい」
ふり絞るように京極真は頷いた。
不実もいけない。
いつでも誠実であらねば。
でも、どうしたらいいのだろう?
彼女のお願いはいつも愛らしくて、どんなことでも聞いてしまいたくなる。
自分にもっと力や才能があれば、どんなことでも出来るのに、いまだこぶし一つ境地に至らず、修行の身だ。
彼女のころころと表情の変わる瞳が、彼をじっと見つめている。
彼は掌を握りしめた。
あの、憎らしい気障な怪盗ならば彼女の喜ぶ言葉ひとつ、軽快に容易に紡げるのだろう。
甘いささやきで彼女の耳を満たすことが出来るのかもしれない。
たった一言で彼女に喜びや笑みをもたらすことが出来るだろう。
そう考えると深く囚われるようで、彼は背筋を伸ばした。
肉体は心で、心は肉体だ。
彼女はどこか心配そうに彼を見つめている。
「真さん、そんなに思い悩まなくても、」
「園子さん」
「……なに?」
彼は、勇気を振り絞った。
「いつも、園子さんのこと、可愛いと思っています。すみません、だから思っていることは何でも言えません」
「…………どうして?」
彼は気づかなかったが、彼女の声には甘い媚が含まれていた。
彼はこれでもかと拳を握り、拷問の末に吐き出す言葉のように打ちひしがれて告げた。
「自分は、あなたのことになると、自制が利かないからです」
固く握った拳に柔らかい手が添えられた。
「そうなの?」
「そうなんです」
「そうなんだ、へぇー」
「軽蔑されるかと、思います」
「へえー」
「申し訳ない」
「ふーん、そうなんだー」
彼は罪悪感で顔を上げられなかった。
視線を上げて彼女の顔を見られなかった。
その時の彼女の微笑みを見られなかった。
「それじゃ許してあげる」
「あ……」
彼はそこでやっと顔を上げる。
「面目なく……」
「いいのいいの!ただの思い付きだったし!」
「有難うございます」
「そうだ、さっきおしゃれなカフェ見つけたんだ。一緒に行こ?」
「はい、園子さんの行きたいところであればどこでも」
きゅ、と彼女が手を握った。
彼はどっと手汗が滲むのが分かった。汚い、とわかっていて、離す事も拒否もできなかった。
彼女は微笑んでいる。さっきと同じ笑い方で。彼は、動揺してやはり気づかない。
自分の頭に浮かぶ考えを言葉にするとやはりどうなるのか、そのことばかり考えていた。
#あむあず /お願い
「安室さん、今日はお喋り禁止ですよ」
梓はそう告げた。仕事で疲弊した男の声ががらがらで、風邪には至ってないが今日はお店はマスターの貸しきりで、二人とも珍しく休日だ。折角なので休んでもらおうと出し抜けに梓は提案した。安室は、いえ、と言ったがその続きは喉を動かしただけで終わった。梓は小指を立てて促すと安室はおずおずと小指を絡ませた。約束ですよ、と言って梓が安室にキスをすると安室はまんざらでもない顔をしてにこっと笑う。呪いがキスで解けるなら、約束もキスで与えられるのだ。心を決めたのか、ベッドに行き、寝始めた。休日といっても安室の場合は完全にオフではなく、安室は知らないが梓は安室の携帯が別にあることを知っている。特に追求したりしない。ゆっくり眠れるように梓はそーっとパソコンに向かい、ヘッドホンをつけて、最近はまっている配信ドラマの続きを見ることにした。大尉はくるりと丸まってテーブルの下で寝ている。のんびりと飲み物を見ながら、梓は暫くドラマの世界に浸っていた。
ふっと、気配がした。安室が起きたようだがすでに傍にいた。わ、と梓が驚くものの安室は笑うだけだ。ヘッドホンを取ったが、安室は何も喋らない。そういえばお喋り禁止を約束したことを梓は思い出した。ドラマを見ていてからすぐ忘れてしまっていたが安室は律儀だ。いつもよく喋る雄弁な人だから、黙っていると不思議な感じがした。表情や仕草からしか伝わらないから、まじまじと改めて安室の顔立ちを見詰めるとやっぱり甘く整った顔立ちの男の人だった。各身体のパーツも整っていて、スタイルも良い。この平凡な部屋に居るのが不思議な気がした。梓は楽しくなって笑うと安室が首を傾げた。
「あ、違うの。ただ改めて、安室さんが部屋にいるのが不思議で」
不思議って、という風に眉が下がった。安室が梓を抱き締めた。言葉ではなく、行動で示したということだろう。何度かキスが降ってくる。饒舌な言葉をもつ男が言葉を取られると行動が饒舌になるのかもしれない。梓は安室の背中を軽く叩く。止めるつもりだったが、安室はにこりと笑った。覆い被さるように倒れてくる。床と安室の身体に挟まれて、梓は身じろぎした。重いですよ、と抗議すると安室は満足したように体重をずらしたようだった。少しほっとしたが、拘束は解けず、自分に寄生する大きな虫みたいに安室は張り付いて離れない。疲れてるのかもしれないと梓は思った。腕を少し動かして、安室の頭を撫でると安室が梓を覗き込んだ。瞳がぶつかる。無数の色に溢れた瞳が、柔らかく細められる。言葉を持たない安室は可愛いのかもしれない。安室は気が済んだように、梓を抱き込んだまま、また眠ってしまった。梓は身じろぎしたが、思いの外動けない。何かの技がかかっている気がする。結構迷惑だったが、たたき起こせばすぐ安室は起きるだろう。まあいいかと、梓は目を瞑った。安室の規則正しい寝息が聞こえる。リラックスしているのか、深い呼吸だった。梓はその鼻と唇を手で塞ぐ。
ゆっくりと、安室の瞼が開いた。寝起きと思えない透明で意思をもった眼差しが、梓を捉えた。梓は、額にキスをした。安室は何も言わなかった。梓は手を外した。呼吸を再開させた安室は、少し笑った。無性に甘ったるい、視線はゆっくりと外れて、梓を抱き締めなおすと安室は再び目を瞑った。梓は呼吸に合わせて微動する睫毛を見詰める。
約束ではなく、呪いだった。だがそれが、二人を阻害することがないのは明白だった。紡がれるはずだった一時の言葉は溢れて、真実みたいに崩れ去るとき、安室の第一声は何になるだろう。大尉が鳴いた、ただの寝言であった。
#京園
鈴木財閥のご令嬢に恋人ができたいう話はまことしやかに、社交界に広がっていった。あの鈴木財閥の後継者になるのは彼女という話が有力で密かに彼女の地位を狙う男たちにとっては衝撃的な話だった。彼女を誰が落とせるかという密かなゲームは彼女が18歳になる頃始まる予定で、開催まであと数ヵ月だった。すわどこかの著名な一家との政略結婚かと調査の手を伸ばしてみるものの、件の恋人が400戦無敗の衝撃の貴公子ということで、ますます彼らは混乱した。何故?格闘家とご令嬢か?そうなると気に入ったのは彼女の方でその地位を使ってわがまま放題に彼を手篭めにしたのだろうか、それならばまだ付け入る隙はあると勇み足で彼らは、ご令嬢と格闘家が出席するというパーティーに出る情報を聞き付けて参じたものの、脆くもその企みは崩れ去った。
相思相愛ではないか。
初々しいほど場の空気に飲まれて緊張する彼を、彼女はからかいながらエスコートしてゆく。色素の薄い彼女の淡い紫のやわらかな光沢のドレスと彼の鍛えられた肉体を映えさせるようにあつえられた直線のスーツは見事に調和しており、それは二人のバランスの良さを見事に示すものであり、お互いが話すときにじっと相手を見つめる眼差しは思いやりがあって、温かった。蕩けるような甘さも混在しており、仕草ひとつとっても、誰かが付け入る隙などまるでないように思えた。
こうしてみると彼女はひどく魅力的な女性で、気の強そうなミーハーな女に思えていたものの、その心根がひたむきに一人の男に向かう時、なんとも言えぬ、豊潤で大きな器を持つ、とても愛情深い清らかな女に思えたのだった。
彼らは自らの見る目のなさに失望したものの、そういった不埒な視線を気づかないわけがない彼であったから、彼女の横顔からすっと目を外し、刀の閃きに似た鋭い視線を真一文字に彼らに向かって切りつけるが如く、浴びせた。その瞬間彼らは冷や水どころか氷水を浴びせられたように震え上がった。決して野蛮ではない獣は、むしろ知性があるがゆえに恐ろしいのだと彼らはその時初めて思い知ったのだ。これは自分達の手に追えないと、彼らは表向きはスマートな素振りのまま、手足などはがくがく震えながらその場を撤退した。
その事に何も気づかない彼女は、彼らの後ろ姿を見て、あら!来ていらしたんだわ。挨拶できなかったわね、と軽やかに笑った。彼は、途端何もわからなくなったように混乱したような面持ちで、園子さんの言うとおりです、と応えた。それってつまり、どういうこと?と眉をあげて見せた彼女は彼の彼女を好きすぎる余りの不審な行動に慣れていたから、今度はあれを食べましょ、と新たな料理へと彼を導く。彼は微笑んで、付き従ってゆく。彼は分かっていたし、彼女は分かっていた。ここが、一種の狩り場であることは。しかし、それでも構わなかった。二人いて、何も困ることはなかったからだ。
#特殊設定梓さん先天性男性化と安室くんの話続きを読む安室くんが店に入ってきて、自…
#あむあず
#特殊設定
梓さん先天性男性化と安室くんの話
安室くんが店に入ってきて、自分が外れの方になってしまった。まあそれはいつものことだから気にならない。かっこいい男がいつだって勝つ世の中だ。
「榎本さん、これでいいですか?」
コーヒーの試飲だ。一通り安室さんはハンドドリップの方法もわかっている、調理もできる、注文の取り方もすぐ覚えたし、なんならメニューを暗記している。一教えると十を知ることができるのだ。
「安室くんって、何でもできるね」
「そうですか?まだまだですよ。これならもご指導お願いします、榎本先輩」
僕は思わず肩を竦めた。童顔でタレ目、なんとなく油断してしまいそうな微笑みに対して安室くんの眼差しはどこか鋭い。狼が羊の皮をかぶってるみたいだ、なんて決めつける証拠はないんだけど、男同士の連帯にいまいち入りきれなかった自分からして、確実に上位プレイヤーだろう安室くんの柔らかさは少し胡散臭い。そしてそれが悪いわけではない。探偵をしているんだし、揉まれたところもあるのだろう。
「安室くんは今日は夕方までですよね、食べていきますか?それともお持ち帰り?」
「いいんですか?うーん、どうしようかな」
「マスターが新しいお米のブランドを仕入れしたみたいで、おにぎりでもいいですよ」
「いいですね、おかずは何か……」
「ウィンナーありますよ、パスタ詰めてもいいですよ、食べるでしょう」
「炭水化物ばかりはあんまり」
「えっ、あ、そうですか」
安室くんが可笑しそうに笑った。
「榎本さんは平気ですか?炭水化物に炭水化物」
「え、そりゃもう。食べますよ、食べません?」
「こう見えても三十手前なので」
「ほぼ同世代でしょう?」
「それは嬉しいですけど」
「フライは?」
「おにぎりだけで。あとは味噌汁作ります」
「じゃあ、ウィンナーも。オムレツ作りますから」
「食べさせようとしてます?」
「なんとなく悔しくて」
「君も通る道ですよ」
「本当ですか?」
「人によりますけどね」
「プリンはどうします?!」
「ははは」
てらいなく安室くんが笑う。笑い声にお客さんがカウンターを振り向いた。イケメンの屈託ない笑顔にあら、という顔をして、そもそも飲食店で雑談はどうなのかという問題は喫茶ポアロだから、ということで納得してもらいたい。マスターには、二人が喋ってるとお客さん受けががいいみたいだと言っていた。それはどういうことなのか。
「もしかして、榎本さん、今お腹空いてますか?」
「えっいや、そんなことは…………ありますが」
「いいですよ、食べてきても。何か作ります?」
「それは、うーん。あとで休憩がありますから」
「真面目ですねえ」
「違います、ごはんの話をしていたからですよ。ちゃっちゃと弁当つくっちゃいましょう」
「有り難うございます」
「それよりテーブル任せます、見ていてください」
「はい、お任せを」
安室くんは笑って敬礼して見せた。僕はオムレツを作って持ち帰り用のパックに詰めたあと、何かケチャップで文字を書いてやろうと考えた。ひとしきり悩んで、おつかれさま、にした。いつも大変だろうから。目敏く気づいた安室くんが、笑った。男の僕から見ても安室くんはかっこいい。でもやっぱりどこか胡散臭い。そしてそれは安室くんを毀損しないのだ。ラップでごはんをくるんで、おにぎりを握る。何を考えてるんですか、と安室くんが言った。空いたお皿を下げて、水に浸ける。僕は考えながら言う。
「安室くんが懐いたらいいなって」
「え?」
「いや、やっぱり今のなしで」
「聞いちゃいましたけど」
「安室くんは後輩だからね」
僕はおにぎりを作る。自分が食べられる量。安室くんは少し困った顔をした。僕はちょっと笑う。困ればいいんだ。たまには。時々、そっちのほうが気が楽だろうから。
畳む
梓さん先天性男性化と安室くんの話
安室くんが店に入ってきて、自分が外れの方になってしまった。まあそれはいつものことだから気にならない。かっこいい男がいつだって勝つ世の中だ。
「榎本さん、これでいいですか?」
コーヒーの試飲だ。一通り安室さんはハンドドリップの方法もわかっている、調理もできる、注文の取り方もすぐ覚えたし、なんならメニューを暗記している。一教えると十を知ることができるのだ。
「安室くんって、何でもできるね」
「そうですか?まだまだですよ。これならもご指導お願いします、榎本先輩」
僕は思わず肩を竦めた。童顔でタレ目、なんとなく油断してしまいそうな微笑みに対して安室くんの眼差しはどこか鋭い。狼が羊の皮をかぶってるみたいだ、なんて決めつける証拠はないんだけど、男同士の連帯にいまいち入りきれなかった自分からして、確実に上位プレイヤーだろう安室くんの柔らかさは少し胡散臭い。そしてそれが悪いわけではない。探偵をしているんだし、揉まれたところもあるのだろう。
「安室くんは今日は夕方までですよね、食べていきますか?それともお持ち帰り?」
「いいんですか?うーん、どうしようかな」
「マスターが新しいお米のブランドを仕入れしたみたいで、おにぎりでもいいですよ」
「いいですね、おかずは何か……」
「ウィンナーありますよ、パスタ詰めてもいいですよ、食べるでしょう」
「炭水化物ばかりはあんまり」
「えっ、あ、そうですか」
安室くんが可笑しそうに笑った。
「榎本さんは平気ですか?炭水化物に炭水化物」
「え、そりゃもう。食べますよ、食べません?」
「こう見えても三十手前なので」
「ほぼ同世代でしょう?」
「それは嬉しいですけど」
「フライは?」
「おにぎりだけで。あとは味噌汁作ります」
「じゃあ、ウィンナーも。オムレツ作りますから」
「食べさせようとしてます?」
「なんとなく悔しくて」
「君も通る道ですよ」
「本当ですか?」
「人によりますけどね」
「プリンはどうします?!」
「ははは」
てらいなく安室くんが笑う。笑い声にお客さんがカウンターを振り向いた。イケメンの屈託ない笑顔にあら、という顔をして、そもそも飲食店で雑談はどうなのかという問題は喫茶ポアロだから、ということで納得してもらいたい。マスターには、二人が喋ってるとお客さん受けががいいみたいだと言っていた。それはどういうことなのか。
「もしかして、榎本さん、今お腹空いてますか?」
「えっいや、そんなことは…………ありますが」
「いいですよ、食べてきても。何か作ります?」
「それは、うーん。あとで休憩がありますから」
「真面目ですねえ」
「違います、ごはんの話をしていたからですよ。ちゃっちゃと弁当つくっちゃいましょう」
「有り難うございます」
「それよりテーブル任せます、見ていてください」
「はい、お任せを」
安室くんは笑って敬礼して見せた。僕はオムレツを作って持ち帰り用のパックに詰めたあと、何かケチャップで文字を書いてやろうと考えた。ひとしきり悩んで、おつかれさま、にした。いつも大変だろうから。目敏く気づいた安室くんが、笑った。男の僕から見ても安室くんはかっこいい。でもやっぱりどこか胡散臭い。そしてそれは安室くんを毀損しないのだ。ラップでごはんをくるんで、おにぎりを握る。何を考えてるんですか、と安室くんが言った。空いたお皿を下げて、水に浸ける。僕は考えながら言う。
「安室くんが懐いたらいいなって」
「え?」
「いや、やっぱり今のなしで」
「聞いちゃいましたけど」
「安室くんは後輩だからね」
僕はおにぎりを作る。自分が食べられる量。安室くんは少し困った顔をした。僕はちょっと笑う。困ればいいんだ。たまには。時々、そっちのほうが気が楽だろうから。
畳む
#京園
運命だと思った、二度、運命だと思った。笑われてる女子がいた、大声を上げて、なりふり構わず、拳を振り上げて、顔を目一杯動かして、ひたむきに友人を応援している姿は面白かったのだろう、実は彼女を一度見たことがあった、他校の生徒を探して、キャーと騒いでいる姿を本当は見たことがあった、そういう女子を、気にかけたことはなかったが、彼女はよく動くから、一瞬目についた。視界に触れて、それで、一旦忘れたのだと思う。
彼女の色素の薄い茶色の髪が、暴れるように乱れて、大きく開けた口が、いけー!とか、やれー!とか、物騒な言葉をもたらして、友人の、一挙一動にハラハラドキドキして、祈るように目を伏せて、そして射抜くような気合いの入った眼差しで、蘭!あんたならできる!と叫んだ。
自分の神経のひとつひとつが、細胞が、彼女にまっすぐ向かっていって、すんなりと理解をした、これが、恋なのだと。
同時に分かっていた、これは、叶うことのない恋なのだと。
「どうしたの、真さん」
瞬きする。
「いえ、ちょっと時差ボケがあったみたいで」
「大丈夫?ホテルで休もっか」
「え?いえ、大丈夫です」
「いーのいーの、一度アフタヌーンティーの試食に来てくれって頼まれてたから。近くのホテルだし、このまま行こう」
彼女は自然な動きでタクシーを呼び止めて、ホテルの名前を告げる。そういえばこの前蘭がね、と楽しそうに話をしているのを聞いている間にタクシーは目的のホテルに到着する。鈴木財閥の所有するホテルだった。彼女は、ボーイに名前を告げて支配人に取り次いで貰うように頼み、彼女のことを知っているホテルマンの一人が園子さまと、ラウジンカフェへと案内する。ドリンクが運ばれてくるまでごく自然で、彼女は特にその事を殊更誇示するでもなく、当たり前に享受している。彼女はお喋りを続けていて、それは普段近くにいない時間を埋めてくれるようで愛らしかった。支配人が現れて、彼女は彼が休める部屋を用意してくれる?と言う。それから部屋にアフタヌーンティーを用意して、と告げる、支配人は当然と応じて後は待っていれば眺めのいい部屋に案内されるだけだった。実家の旅館を思い出す。オーシャンビューの一望を彼女はまあまあだね、と笑って、ほら、ゆっくり休んで、と自分をベッドへ促した。もごついていると、いいからいいから、と引っ張って、
「それともなあに?寝かしつけてくれってこと?」
と、いたずらっぽく笑った。子守唄なら歌えるかも、と言うので、聞いてみたい気がしたが、これ以上は墓穴な気がして、ベッドに潜った、自重を包み込むようなゆったりとしたマットレスに清潔なシーツ。掛け布団もふわりと軽く温かかった。外はあんなにも暑いのにここは、冷房が効いていて、寝具の中にいるのが、心地よかった。快適だった。目を瞑っているとマットレスが少し揺れて、彼女の気配がした。もう、眠った?言葉は喉に貼り付いて、彼女の柔らかで華奢な指先が自分の髪を触るのが分かった。
「んー絆創膏剥がしちゃおっかな」
思わずびくりと、身じろぎするとくすくす彼女は笑った。
「ウソウソ、やっぱり起きてたんだ」
「眠りに落ちる寸前でした。でも本当にいいんですか?退屈ではありませんか」
「いいの。滅多に会えないのに、ゆっくり過ごすのって逆に贅沢でしょ」
起きたら、アフタヌーンティーしましょ、と彼女は言う。盛大に甘やかされている気がして、不意に羞恥が昇った。それを気取られぬように、布団を被った。
「おやすみ、真さん」
彼女が微笑んだ、のが伝わる。彼女の周りの空気が揺れて、いつもそれが自分のところまで振動する。共鳴する。それが、独りよがりな心情だと分かっている。
そっと彼女を伺った。彼女は、窓の外を眺めている。真夏の青空は、痛々しいほど青く、目映い。ゆっくりと彼女は伸びをして、自分にとっては不釣り合いなほど高級な一室であっても、彼女にとっては日常のものでしかなく、自宅のような様子で、ソファに座り、携帯を触る。
実家の旅館に彼女がやって来たのはたまさか偶然で、理由は未だ分からない。運命だと思って、嫌がられると思って、嫌われていると思って、執着していると思われて、執着していて、どんな理由をつけていたって、人命を救ったと警察に表彰されたって、自分はただ、好きな人に理由をつけて付きまとっていたのは、事実だったから。彼女を助けられてよかった、と思う。こぼれ落ちて行くのに耐えきれなかったのだ、理由をつけて、固執した。好きだったから。好きだから。
自分だって、応援されたい。
あの時、乱暴な衝動で沸き上がった、強烈な自我を。あんな風にひたむきに、愛されたいと願ってしまったことを。
やわらかな寝具の中で、彼女を覗き見している、まだそんなことをしていて、好きだって言われてからも、自分が見つけたように、彼女が誰かを見つけたり、見つけられたりするかもしれなくて。なのに、遠く離れている。
目を瞑る。
夏は彼女に相応しくて、彼女の生き生きとした情熱は、太陽に劣ることはなくて、想像とした夏と今は違っている。ゆっくりと起き上がって、ずれた時間が、太陽の存在が、歯車を少し軋ませて、どうしたの?のどが渇いた?とやってきた彼女を、掴まえた。
優しい肉体は柔らかで、自分はもっと強靭になろうと思った、世界が滅んでも。
彼女だけは生きてほしい。
頭を押し付けた彼女の胸部からとても早い鼓動が聞こえて、血の流れを感じて、ぎこちなくあやすみたいに、彼女が背中を撫でた、悪い夢でも見たの?
呼吸して、呼吸して、自然と彼女の体臭が入り込んできて、壊れないように腕の力を調節した、ーー少し。
疲れているみたいです。
名前に反して嘘をついた、狂わぬように。ここが、嘘みたいだから。海の音が聞こえる、遠くからどこまでも。響いてくる。
二度、運命だと思った、浅ましさで引き寄せた、彼女を救ったのではなくて、あの時救われたのは、自分こそだったのだ。
#あむあず
新しい手品を練習してるんです、と彼が言った。彼女は、興味をそそられて、え?どんなのですか?と尋ねる。彼はたれ目を細めて、入れ替わりマジックです、と言った。それって、人と人とが入れ替わる分ですか?と彼女は驚いた。それって結構大技なのでは?
彼は、得意気にも頷いた。
「ここに安室透がいるとします」
彼は手慣れた仕草でカップを置いた。
「それで、反対側には別人がいます」
もうひとつ同じカップを置く。
「うんうん」
「で、入れ替わる」
彼は二つのカップを入れ替えた。
彼女の見ている前でもう一度。
そしてまたもう一度。
「どちらのカップが安室透だったか、分かりますか?」
「えっ」
カップは同じもので。
彼はかなり手先が器用で。
シャッフルされたそれらは、どれがどれだか分からない。
「うむむ。でも、マジックだから、種も仕掛けもあるはず」
「そうですね」
「うーん……これを安室さんがやるんですか?」
「そうですねえ」
「えーっうーん、わかりませんよぉ」
「ちなみにこちらが安室透です」
彼は笑いながらカップの裏を見せた。そこには子供の悪戯なのか、車のシールが貼ってある。彼女は思わず笑った。
「安室さんは車がすきなんですね」
「それはもう、愛車を大事にしてますね」
「じゃあこれが安室さんですね。今度から裏を見たらいいんだ」
「大事なのは観察。僕は触らないで、とも言ってないですから、よく確かめることも推奨です」
「なるほど、それじゃ、安室さんが入れ替わっても大丈夫ですね」
「梓さん次第ですね」
「がんばります。いつやるんですか?」
「準備ができた上で状況次第ですね」
「楽しみにしてますね」
「はい」
それじゃ、コーヒーでもいれましょうか、と彼は言う。おやつといきましょうと、彼女は笑った。一見同じ見かけのカップにコーヒーが注がれる。でもそうすると、彼女には見分けがつく。彼はいつもコーヒーにはミルクをいれているから。彼女は微笑む。そういうことを、たくさん知ってることを彼は気づいてないから。いつか、驚かせてやろう。手品のあとで。
*
壊れていたんですよ、キーホルダーが。さも恐ろしいことのように榎本梓が語るので、安室透は食器を磨いていた手を止めた。
「…………キーホルダーなら壊れることもあるでしょうね?」
「でもうちの店のキーホルダーなんですよ?!」
マスターが何を思い立ったか、うちの店のロゴキーホルダーを作ってみようと言い出して、あれやこれやと知人のデザイナーに頼んであっという間に限定50セットのポアロのロゴキーホルダーは出来上がったのだ。面白半分に常連たちに配ると結構面白がってくれて、それが呼び水となり、在庫はあっという間に捌けていった。梓と安室も一つずつ貰っていた。案外少なかったね、今度は200セットでいこうかとマスターはノリノリで、どうするんですか?と聞いたら毛利小五郎探偵事務所ロゴと合わせ売りするから、あっという間に売れちゃうでしょとマスターはどや顔だ。案外いけちゃうかもなと思った二人はそれ以上話題をさわらなかった。さて、キーホルダーだ。そのポアロのロゴのキーホルダーが壊れたものが、今朝出勤してきた梓が店の前で見つけた。これって事件じゃないですか?!と言う梓に、やんわりと安室透は笑う。
「どうでしょう。常連客の方が落としたものをしらずに通行人が踏んだのかもしれませんし」
「それはそうですけど、悪い意味があったらどうするんですか?」
「ものが壊れることに意味はありませんよ」
「それって探偵としては正しいんですか?」
「探偵としては、謎を作るより謎を解きたいですねえ」
「安室さんの名探偵!」
「有り難うございます」
「でもよくよく考えたらそうですよね、わざとじゃないだろうし。ちょっとびっくりしちゃっただけで。すみません、お騒がせしました」
「いえいえ、僕も現物をみたら気になるかもしれませんしね。その壊れたキーホルダーはどうしたんですか?」
「処分しちゃいました、ごみの日でしたし」
さらっと梓が言った。安室は瞬いた。気にする割に処分が素早い。
「あ、駄目でした?!証拠品?!」
「いえ、そんなことは」
「すみません、マスターが見つけると気にするかなと思いまして」
よくわからない人だからそれはありえるかもしれない。
「いいことかもしれませんよ」
「いいこと?」
「ポアロの新しいロゴが出来るとか?」
「それはちょっと寂しいかも」
「はは、ですね」
その話は一旦それで終わった。梓がすっかり忘れていた数日後、安室が言う。
「壊れたキーホルダー、毛利さんのものみたいですよ」
「え?……………………あぁ!」
「完全に忘れてましたね?」
「てへへ」
「昨日マスターと話してましたよ、酔って帰ったときにキーホルダーなくしたって。それで、なんか音しませんでした?ときいたら、そういやなにか踏んだなって」
「あー~」
想像が出来たという、あー~だ。
梓が笑った。
「なんてことありませんでしたね」
「そうですね」
安室がふと笑った。
「マスター、今度は強化プラスチックで作ろうかなって言ってましたよ」
「えぇ?」
「銃弾で割れないくらいの」
「えぇ、本気ですか?」
「そうなったら面白いですよね」
安室透は夢想する。いつか自分が心臓を撃たれた時、それを防ぐのがポアロのロゴのキーホルダーならば。
梓は怪訝な顔をしている。
「それってキーホルダーにできるんですかね」
「さあ、どうなんでしょう」
一拍おいて二人は笑い合った。
喫茶ポアロは今日も穏やかに営業中だ。
*
すっかり泥だらけになって帰ってきた安室に梓は犬を思い浮かべるべきか、子供を思い浮かべるべきか、少し迷った。そんな泥だらけの状態で店にはいられても困るし、何より衛生的に大問題だ。というわけで、ちょっと待っててくださいと梓は断り、植木用の蛇口を捻ってホースを掴み、安室に向かって噴射させた。幸い暑い日でもあったから、風邪は引かないだろうが、店の前での行動に通行人がびっくりしたが、安室が泥だらけなのを確認すると、あぁ、みたいな顔をして去っていく。基本的に米花商店街は懐の広い人が住んでいるのである。
けらけらといつになく、楽しげに安室は笑って水を浴びている。梓が最初迷った答えは、この際両方だった。犬でもあったし、子供でもあった。その内、女子高校生と小学生が我が家に帰ってきて、おおよそ玄関前で繰り広げる水浴びに待ったをかけて、シャワーを貸し出してくれうことになった。
ごめんね、蘭さん。
いいえ、困ったときはお互い様ですから、
とはいえ、どうしてこの事態に?とコナンが問いかけて、梓はかくかくじかじか説明した。近所の公園で子供たちと一緒に泥団子を作ってたんですって。
何やってんだよ、公安というかすかなぼやきに答える者はおらず、いやー助かりましたと晴れ晴れとした笑顔で安室がポアロに無事戻ってきた。服は常にロッカーに着替えを用意しているので問題はなかった。
お礼に、何か作りますよ、と言う。
てきぱきと調理し始めた安室に、三人は顔を見合わせる。
梓が息を吐くようにして笑った。
楽しかったですか?安室さん。
安室が笑った。
手伝いますよと、梓が声をかけ、二人であれやこれやとしはじめるので、今度は蘭とコナンで顔を見合わせる。少し気持ちがわかるかもと、蘭が呟いた。コナンは不思議そうな顔をする。蘭は、笑う。新一が楽しそうなときって、結局許しちゃうから。コナンは蘭の顔をみて、カウンターの中にいる二人を眺めた。
自分達もこんな風に人から映るのだろうか。そう考えると、少し面映ゆい気がした。
特製ポアロスペシャルサンデーはアイスとフルーツが山盛りで、笑ってしまうほどだった。
安室がお土産に持って帰ってきた、ぴかぴかの泥団子は、看板に残されている。みんな、これは何?という顔で、しかしなにも言わず、行き交ってゆく。夕日に眩しく、輝く、ぴかぴかに光る金の玉だった。
2024年1月11日 この範囲を新しい順で読む この範囲をファイルに出力する
#あむあず
「安室さんって、去年のクリスマスはどうでした?」クリスマスの準備をしているのだから聞かれるのは当然のことだろう、会話のひとつとして彼女は言い、彼はなんでもないことのように返した。
「仕事していましたね」
「探偵さんは休みがなくて大変ですね」
「ええ、まあ、そういう人々が浮き足だってる時にトラブルは起きやすいですから」
「今年は大丈夫なんですか?」
「尾行するよりかはケーキを売る方がいいですから」
「夢がありますもんね~」
大変ですけど、と彼女が腕を擦った。先程まではクリームをたくさん泡立てていた、マスター発案のケーキの受注は、大人気だ。そもそもマスターの顔が広いから、ふらっと出先で受注してくる。さすがにこれ以上は間に合わないから、受付はやめている。商店街にはケーキ屋もあるから、その折り合いもある。
「梓さんはどんなクリスマスでした?」
「私も仕事ですよ」
「去年はケーキの販売なかったんですよね」
「その代わり商店街のパーティーが」
納得。
二人で笑った。
「そういえば昔ケーキ屋さんになりたかったような、気がします」
彼女が言う。
「夢が叶いましたね」
「そうですね、安室さんは何になりたかったですか」
「なってますよ」
「探偵に?」
彼は笑った。
「いいなあ」
「どうして」
「ちゃんとしてる感じがするので」
「夢を叶えるのが?」
「違います?」
「梓さんも、でもそうでしょう」
「ははは」
彼女は冷蔵庫を見つめた。新しく倉庫にでかいやつが導入された。来年もこの人はここにいるのかなと彼女は思った。
「マスターのクリスマスケーキってどんなかんじですか?」
「お酒の味ですよ」
「へー」
「ジャムが塗ってあってスポンジに洋酒が浸してあってクリームは滑らかで、美味しいですけど、子供向きじゃないかも。今年も作るみたいですよ、常連さんには」
「食べてみたいですね」
「作ってくれますよ、きっと」
「大人ですもんね」
「マスターはサンタクロースだから」
「それは冗談ですか?比喩ですか?」
「真実ですよ」
彼女は言った。
彼は二年前のクリスマスのことも聞こうと思った、それ以前のクリスマスも。
「赤が嫌いなのってクリスマス由来とか?」
「秘密です」
「そっかあ」
サンタクロースは好きでした?と言われて、彼は笑った。
「善良な人は好きですよ」
「大人目線の解答ですね」
「不法侵入はどうかと思いますが」
「探偵もそうなんじゃないんですか?」
「犯罪者と一緒にされるのは心外ですね」
「すみません」
「いえいえ、どうも」
彼は帰り支度を始めた、上着を着るついでに言う。
「初めて一緒に過ごすクリスマスですね」
「…………………炎上!」
「がんばりましょうね」
何を。
彼は笑う、送りますよ。彼女はふっと視線をはずした。
「この近くにきれいなイルミネーションがあるって聞きました、よ?」
「クリスマスですからね」
「はい、クリスマスです」
「あっという間にお正月で、あっという間に春ですね」
「はい」
「でも、クリスマスは今だけなので」
「そうですね」
「楽しみましょう」
「目指せ商店街のサンタクロース」
ほんとは、と彼は聞いた。二年前のクリスマスのことを。彼女は笑って、店の外に出た。扉を開けて待つ彼女に彼は肩を竦めた、良い子のもとにサンタクロースはやってくる。彼に必要なのは夜道を迷わず導いてくれる真っ赤な鼻だった、憎むべき赤が世の中にはたくさんあり、しんと冷えた空気が彼女の鼻や頬を赤く染めるのは、しかし、そう悪いことではなかった。
アナウンス
※現在こいくう以外のソシャゲのプレイは休止しています。その為作品はプレイ当時のものとなります。
受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり
R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。
年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。
受け攻め性別不問/男女恋愛要素あり
R18と特殊設定のものはワンクッション置いています。
年齢制限は守ってください。よろしくお願いします。





























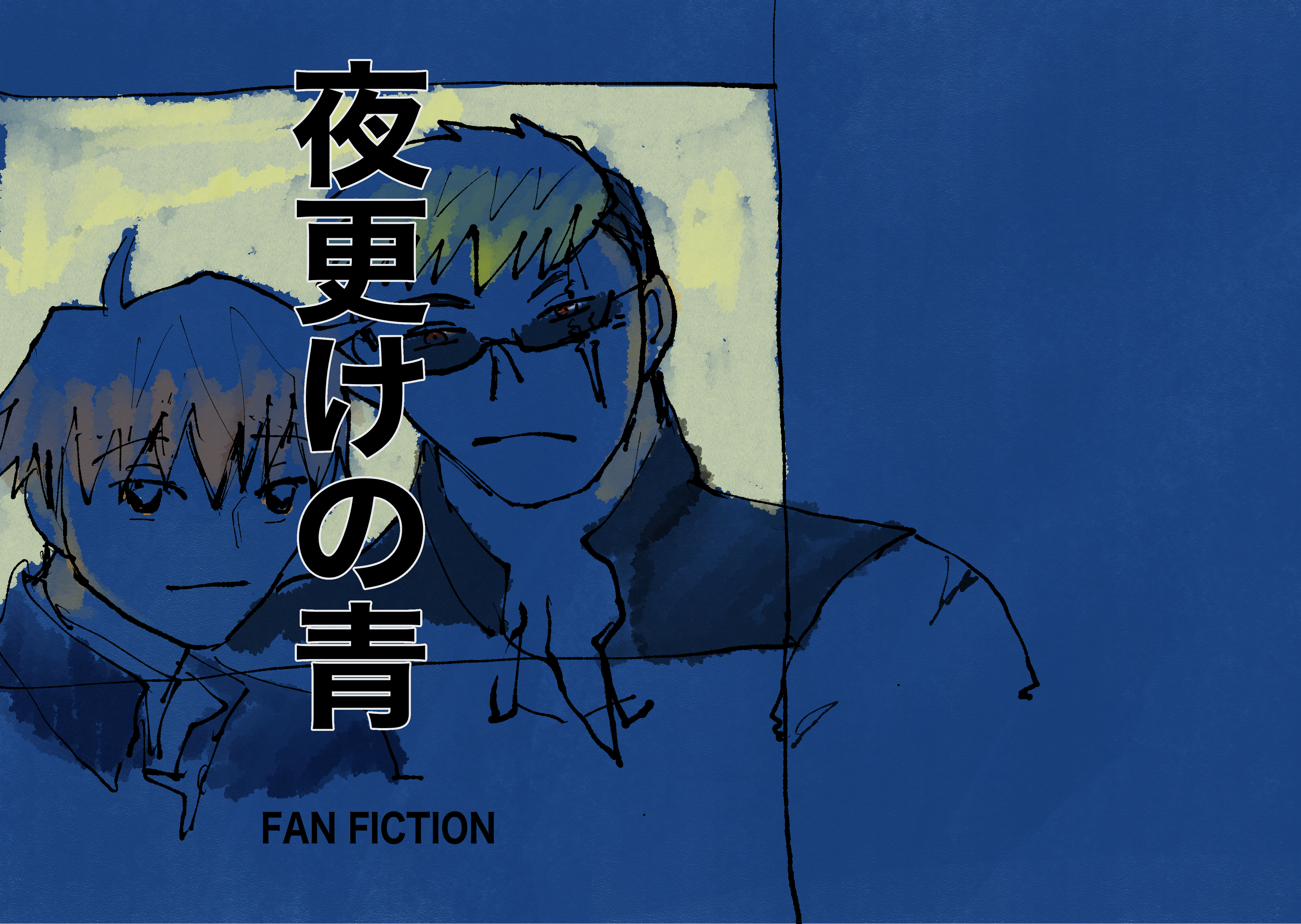
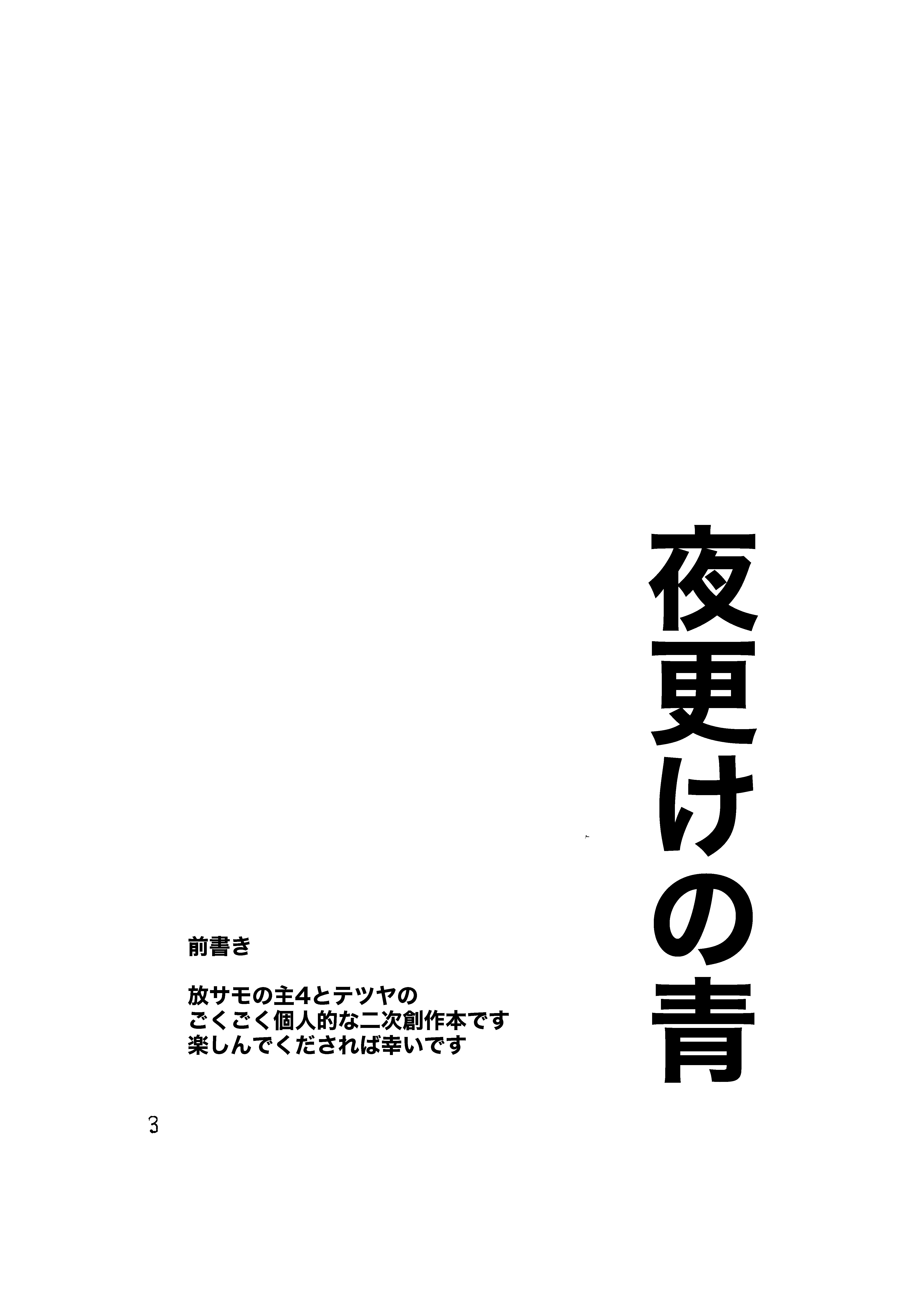




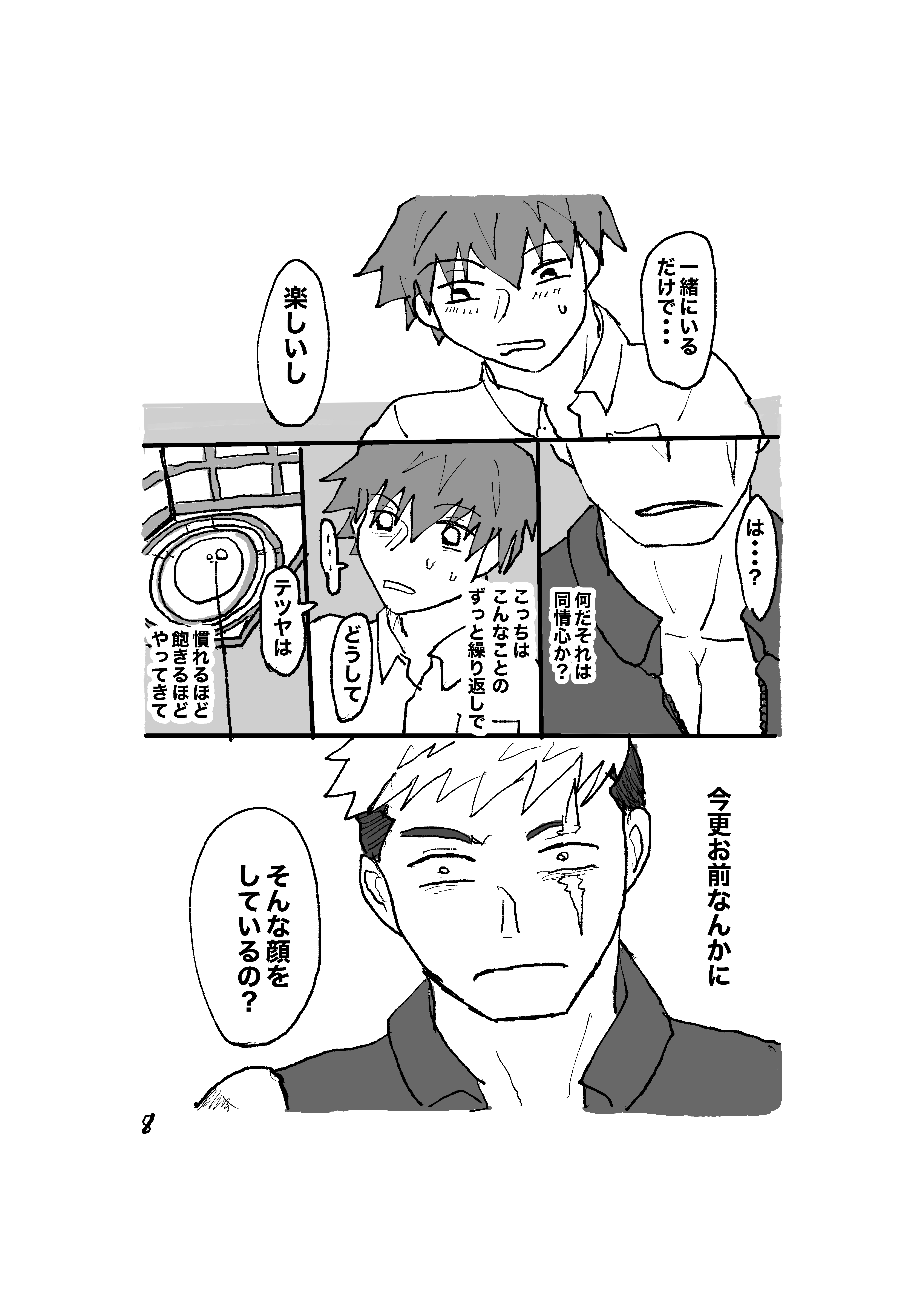













#特殊設定
#あむあず
「犬……」
「……犬……」
奇怪な部屋が喫茶店からの帰り道にあった。別段二人で帰ったというわけではなく、安室がついでに送っていきますよと言うので、梓はまあいいかと思って応じたのだ。安室は珍しく電車で移動するらしく、終電まで少し間がある帰り道で、二人であてもない話をしていたときに建物と建物の間にそれはあった。安室はこの辺一帯の建物を認識していて、ちょっと待ってください、こんな建物は確かなかったはずと、当然と踏み込む安室にちょっと不法侵入では、と梓が腕をつかんだ折にまるで吸い込まれるようにして、部屋に引き込まれたのだ。決して安室が招いたわけではないのだが、実際彼の油断なのでそうと言えばそうだ。反省は直にするとして、気づいたときにはそっけない謎の空間に二人して立っていたのだ。ひとつあるディスプレイのような画面に、「犬プレイをしたら出られます」と書いてあった。言うに事欠いて、犬プレイときた。
「犬プレイってなんですか……?」
「犬になりきるプレイですかね」
「どういう目的なんですか……?」
「人が犬になっているところを見たいという変態欲求ですかね……?」
「犯罪なのでは……?」
「まあ色々と法には触れていますね……」
さて、犬である。
きちんと首輪とリードが用意されていた。念のため、扉やらなんやら確認してみたがロックがかかっており、携帯は使えない。もう一台の携帯と無線もそうだ。はて、と安室は考え込んでみたが、少し面倒になった。
「じゃあ、梓さん、僕が犬をしますから飼い主ということで」
「ちょっと待って、どういうことですか、やるんですか、犬プレイ」
「さっさと終わらせましょう」
安室が仕事の顏になった。無駄にきりりとし、なおかつ、にこやかだ。
「梓さん、どうせなら首輪つけてくださいよ」
「うぇええええええ」
「嫌なんですか?」
「いやあ、まあ……はい……」
嫌と言えばかなり、嫌だ。
安室は何故か満面の笑顔だ。
あれ?断れない空気?と気づいて、梓は引きつった。だがまあ、彼女も順応が早いのである。
「わかりました、こうとなれば犬プレイでも猫プレイでもして、さっさと帰りましょう!大尉が待ってるし!」
「その意気です。さすが、梓さんです」
拍手喝采、実際は軽い拍手をして、おだててみる安室だった。
首輪を手に取って、梓は安室の首にかけた。
ベルトを止めるところで、忘れておいた理性が、ぴくりと動いたが、気づかないふりをして、留めた。
首輪をつけた安室と梓は対峙する。
安室の瞳の色がふと揺れて、それが証明みたいに安室は微笑んだ。
「ワンッ」
「え?えー?えー…」
あはは、と妙な笑いを梓は浮かべる。
まるで散歩に行こうというように安室がリードを咥えて持ってきた。
すっと安室が四つん這いになる。
梓は半歩下がった。
が、わんちゃんがしっぽを振ってお散歩を待っている。
「よ、よーしよし」
梓はその髪をなでた。
色だけ見るとゴールデンレトリーバーだ。
首輪の先のカンにリードをつける。
わん、と安室が鳴いた。
いや、犬が鳴いた。
ぐるぐると梓は浸食される気がした。
梓はリードを持った。
金色の毛皮を持つ犬は、ゆっくりと歩き始めた。
梓との散歩を楽しむように、時折ちらちらと梓の顔を見上げる。
かわいい。
もうよくわからなくなってきた。
尊厳とか、人権、とかそういうものを。
壊されているのは自分のような気がした。
人は犬になれるのか。
人を犬と思えるのか。
梓が止まったら、犬も足を止めた。
その前足で、梓の様子を窺うように梓の足を触った。
梓はしゃがみ込む。
わしゃわしゃと頭をなでる。
後頭部から背筋を撫でると尻尾は盛んに揺れた。
犬は、もっと、と欲しがるように前足を掻いて要求する。
犬は梓の顔を舐める。
くすぐったかった。
んぎゅ、と抱いて、一頻り撫でると、耳元で引く声がした。
「開いた」
梓は目を見開く。
安室は何故か、梓にキスをして、ゆっくりと立ち上がった。
上背のある、すらっとした男の人がそこに立っている。
「帰りましょう、梓さん」
梓はなんだかふわふわした頭で頷いた。
それから、外して、と強請られて梓は首輪とリードを外した。
安室は微笑む。
―――気づいたらいつもの帰り道だ。すべては、夢だったのかもしれない。嘘だったかもしれない。酔っぱらっているのかもしれない。酒を飲んでもいないが、コーヒーは飲んだから。いろんなことを聞きたかったが、言葉にはならなかった。取り留めのない話をして、二人は別れた。梓を待っていたのは、大尉で、梓にすり寄って甘えた。そのふわふわの毛並みを撫でながら、梓は今日の出来事をすべて忘れようと思った。
――数日後、梓の許に安室からの荷物が届く。中身を見ないようにしたが、気になった。封を開けると、首輪とリードが入っていた。梓は呆然と、それを眺めた。
犬って。
安室が嬉しそうに微笑んでいる気がした。
畳む