2024年の投稿[10件]
2024年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
夢創作
令嬢転生もの~4
入った部屋は薄暗く、ほんのりとした灯りがベッドサイドにあるだけで、甘い匂いが漂っている。ここが、そういう部屋であることは間違いなかった。細長い窓のカーテンを開けると、夕暮れが差し込む。ブラッドとエーデルワイスの間に沈黙があったが、エーデルワイスが、ぼすんとベッドに腰かけた。
「ブラッド様も」
明るい声でエーデルワイスが言う。ブラッドは一瞬の躊躇いを噛み砕いて、エーデルワイスのとなりに腰を下ろした。スプリングが僅かに軋んだ。言葉を探している時に、エーデルワイスが言う。
「……ごめんなさい、告白されたときに言うべきでしたね。婚約者がいるって。」
「あ、いや、俺が先に知っておくべきだったんだ。君に負担をかけてしまう前に。君のこと、なにも知らないみたいだ」
ブラッドはエーデルワイスの靴先を見た。パーティー用なのだろう、先のとがったエナメルの白い靴だ。ビーズが華美でない程度にあしらわれている。エーデルワイスはすっきりとしたドレスを着ている。仕事というのもあるのだろう、あくまでも目立つつもりがないようなドレスはそれでもとろりとした光沢があり、触れてみたくなるようだった。
「……………ブラッド様」
「え、あっ、はい」
「あの、どうして私を好きになってくれたんですか?」
ブラッドは顔を真っ赤にしたエーデルワイスから視線をそっと外した。今、別のことを考えていた自分を恥じた。
「それは、その。覚えてるだろうか、図書館での話だ」
「図書館」
「君が病気で伏せていた後で、放課後に君と出会った」
「………はい。勉強をするために」
「そうだ。何故そこまで必死に勉強をしているのかと俺は聞いたね。君は医者になりたいと言った」
「……はい」
「また何故かと尋ねたら、君は償いの為だと言った、その時の君が笑うから俺はなんだかさみしくなってしまって」
「さみしく………?」
ブラッドは思い返す。
エーデルワイスは一人で勉強していた。何だか世界の全てを詰め込むみたいに必死に、挑むみたいに。
「君の味方になりたいと思ったんだ。そばで支えたいとも思った。そうすれば、君は笑わなくてもいいだろうと思って。………今も、そんな風に」
ブラッドはエーデルワイスの頬にほんの少し指先を添えた。
「それから君を見ていた。君が何かと戦っているのはわかるよ。だからその手伝いがしたいんだ」
「………………」
それは、と彼女が言った。
「私を好きだと言うことですか……?」
「そうだ。俺は君が好きなんだ」
エーデルワイスの瞳から涙がこぼれて、静かに頬に伝っていく。震える唇が息を吸って、彼女は微笑んだ。
「ーー教えてくれないか。俺の好きな人は君ではないというのは、どういう意味なんだ?」
「それは……」
「関係あるのか?ーー君と、マジョーリカは」
「……ごめんなさい、もう戻らなくては」
エーデルワイスは立ち上がった。
ブラッドは彼女の手を掴んだ。
「エーデルワイス」
「…………」
「必要なら、君を奪う」
彼女は眉を下げて笑った。
「もう、私のことは忘れてください」
「エーデルワイス!」
彼女は部屋を出ていき、ブラッドは息を吐いた。
少ししてからブラッドも部屋を出ると、ヴィーナンテが言う。
「早かったですね、もっとゆっくりしていけばよかったのに」
ライオットが目の前にやってくる。
「お耳にいれたいことが」
いつになく真摯だ。
「嫌な話か」
茶化すように言うと、ライオットは取り合わなかった。
「これ以上、エーデルワイスに近づくのは得策ではないかもしれません」
「何故」
ライオットは言葉を選んだ。
「我々に関わることだからです」
我々に含んだ意味をブラッドは汲み取った。
「楽しみにしていますよ。ーーーー幾つかの、ご支援を」
これで幕引きとばかりにヴィーナンテがお辞儀をした。すでに夜の帳も落ちている。
ブラッドは引き上げることにした。
屋敷に帰っても、今日はお疲れでしょうから、とライオットは話さなかった。自分から言い出したことだろうと言っても、躱すばかりでもやもやした気分のままブラッドは眠るはめになった。
「ライオット、朝だぞ」
慇懃に話かけるとライオットは頷いて見せた。朝から受ける予定だった学園の授業を振り替えて、人払いを済ませたブラッドの寝室で話すことにした。
「グランディアの戦いにて英傑になられたカリウス王はご存じですよね」
「この国の基礎を作ったような王だからな、子供のときからよく聞かされていたよ」
「カリウス王の采配は見事だったと伝えられています。先進的で通常なら考えられないほどに突飛で優れた策で、打ち勝った」
「それがマジョーリカに取り替えられたから、か?」
「しかし、それが真実だったとしたら?」
ブラッドは窓の外を眺めた。
「カリウス王が実はどうとでも知れぬ相手となれば、王としての意義は問われるだろうな、王族としての価値に傷が付く。あるいは、我々にもその傷が及ぶ。王として信じていたものはただの民であり、我々はその子孫でしかないのならば」
「王とは神の神託を受けるもの。カリウス王は未だに人気の高い王です。その土台が崩れるとなると」
「………厄介かもしれないな。だから、エーデルワイスのために、俺がマジョーリカのことを調べると、思わぬ誤解を受けるはめになる、ということか?」
「はい」
「誰から」
ライオットは口をつぐんでみせたが、誠実な従者は言う。
「あなたを厄介がる者たちから」
ブラッドは笑った。
「なら手始めに再度ガハムに話を聞いてみるとしよう。どのみち、マジョーリカのことは調べないといけないようだ」
「ブラッドフォード様」
「まあ、どうにかなるさ。これは、恋の話だからな」
はあ、と呆れたため息を付いてみせたライオットは、では準備をしてきます、と出ていった。
ブラッドはのんびりと大きく伸びをしたあと、思案気に目を細める。
ブラッドフォードは第七王子だ。しかし、その前の兄弟は跡取りである第一王子と第二王子を除き、亡くなっている。事故や病気や、何かで。ブラッドが職務に当たっているのも通常、当たるべき人間が不在だからだ。
「マジョーリカとはなんだ?」
そしてそれは、エーデルワイスに何をした?ブラッドが気がかりなのはそれだけだ。エーデルワイスはまだ何かを隠している。マジョーリカのこともそうと決まったわけでもないのだ。彼はゆっくりと昨日間近に吸い込んだ彼女の匂いを思い出した。
エーデルワイス。
俺の好きな人は、あなただ。
令嬢転生もの~3
ブラッドは書庫担当のガヘムを探した。国の歴史や歴代の王、グランディアとの戦い、カルロッテの真実、リーガルズの星図、作物や治水や気候、ちょっとした世間の話など、いろんなことが書庫には納められている。ガヘムは老齢で、幼い頃より記憶力が優れていて、口上で伝えられている古い話も知っている。未だに衰えをみせない、書庫の番人だった。
ガヘムは書庫の古ぼけた置物のように鎮座している。
「ガヘム、聞きたいことがあるんだが、いいかな」
「……ブラッド王子、今は職務中ではござらんか」
「大事な話なんだ」
ガヘムは用件次第では聞いてやる、という顔をした。ライオットはその様子を見詰める。
「マジョーリカの取り替え話について、知っていることはないか」
ガヘムはブラッドを見る。厳しい眼差しがブラッドを貫いた。
「そのようなことを聞いてどうされるのですか」
「マジョーリカについて調べているんだ。知りたいことがあって。なんでもいい、些末なことでもいいから教えてくれ」
ガヘムを頭を振った。
「本でも読まれるのがよろしい」
「そうだ、本だ。調べるのにいい本はないか?」
「…………」
ガヘムが沈黙を答えとした。ご自分で調べなされ。そう言わんとするようだ。
「ブラッド様」
「仕方がない。忙しいのに手間をとらせたな、有り難う」
ガヘムは応じない。
老齢の男は置物に戻ったようだった。
「ーー何かあるな」
「はい」
「何かヒントを探そう。ライオット、お前の耳はいいだろう。手当たり次第に調べてくれ」
「はい。ブラッド様は職務に戻られてください。ケリーに世話係を頼みますので」
「ついでにケリーの最近の話を聞くとするか」
ライオットが頷いた。
ブラッドが執務室に戻り、ほどなくケリーがやってきた。
「ライオット殿から頼まれました。決算の確認はこちら、署名が必要なものはこちらに分けております」
分厚いレンズのメガネの無愛想な女性で、事務的に仕事をこなす。能力もいい。書類の束を持ってきて、分類する。
「急ぎのものはこちらになります」
「確かこの前も急ぎのものじゃなかったか?チェルシー協会との取引は」
「経費削減ということで、割り引きされたものを買い付けているようです」
「それは適正なのか。そそのかされてやしないだろうな」
「その可能性はあります」
「担当者は誰だ」
「グラントです」
「話を聞いておこう」
「今すぐですか?」
「どちらがいい?」
「焦らすのが良いかと」
ライオットはケリーを気に入っている。
「なら話をしよう」
「何の、ですか」
「最近流行っている詩はないのか?この前、劇が開幕されたと聞いたような。評判はいいようだ。もう観に行ったのか?」
「それは、まあ、はい。行きましたが、手は動かして欲しいです」
「ああ、わかった。それじゃ、作業中に楽しい話が聞きたい。見てきた劇の話をしてくれ」
「はぁ、仕方ないですね」
そこからはケリーの独壇場だった。流れるように語られる役者の一挙一動、演出の印象的なところ、うなる物語にあおられる観客たちの歓声、今もっとも輝く吟遊詩人、ヴィーナンテの麗しき調べ。
「ヴィーナンテ。前もその名前を聞いた」
夢から覚めたようにケリーは瞬いた。
「はい。そうですね」
「有り難う、助かったよ。今日の職務の区切りはこれでいいか?」
「ーーはい。」
「ケリー。お茶を頼んでいる。飲んでから帰るといい」
ケリーはまた瞬いた。一瞬の狼狽はすぐに無愛想に戻り、義務的に一礼して去っていく。
ブラッドはライオットと落ち合う。
「色々聞いてヒントになりそうな人物がおります。会ってみてもいいかと」
「理由は?」
「マジョーリカの話をよくするみたいです。何故なら、自分が取り替えられたから」
「名前は?」
「ヴィーナンテ。今一番の吟遊詩人です」
あれこれと人脈をたどってその日の内にブラッドはヴィーナンテと会えることになった。というのも、王族からの声かけなら興行にとってもよい結果が得られるということと、相手に今日しか時間がないということだ。
「声をかけたのはこちらですが、これは呼びつけられた、ということですね」
「当然だろうな」
招かれたのは、劇場が管理する一軒家で、なんだか賑やかだ。着飾った人たちが行き交い、音楽を奏でていたり、ダンスしたり、酒を飲んでいる。パーティーが催されているらしく、華やかな鳥のようなドレスを着たご婦人の間をくぐり抜け、通されたのは思ったよりも静かで、水中のような部屋だった。壁一面に波紋が広がる。青い光のなか、男とも女とも見分けがつかない美しい人がいた。
「こんにちは。ようこそ、我が家へ」
「あなたがヴィーナンテ?」
「そうです。友よ。出会えて嬉しく思います」
ライオットがブラッドの前に出た。
「こちらは第七王子であられまするブラッドフォード様でございます。ご用件はお聞きしておりますか」
「ええ。なんでも、マジョーリカの話を聞きたいとか。王族の方ならさぞ気になるでしょう」
含みがある。
ブラッドとヴィーナンテの視線が交差する。
「おや、もしや!知りませんか?」
「俺が知っている話があなたの仰っている話かどうかは分かりかねますね」
「これは失礼。ただ、まあ、幾つかありますね」
「幾つか、ですか」
「幾つか、です」
間があった。
「ヴィーナンテ殿の評判は聞き及んでおります。幾つか、支援させていただければと思っているのですが、いかがでしょう」
ヴィーナンテはにこりと笑った。
「では、お耳をわたくしめに近づけてください」
ライオットが眉を潜めた。
ヴィーナンテは微笑んでいる。
ブラッドは耳を寄せた。
「かつて王族にもいらっしゃったのですよ。なんでも、グランディアとの戦いの英雄であらせられる、かつての王がマジョーリカの手によって入れ替えられた王であったとか」
「……………」
そこまで規模の大きな話を見つけようとしていたのではなかったブラッドは戸惑った。沈黙の色を読んで、ヴィーナンテはブラッドの瞳を覗き込んだ。
「おや、まさか」
ヴィーナンテが笑いだした。
「あなたも運のない人だ」
「それがどういう意味かは一先ず置いとくが、マジョーリカが真実なのか、俺は知りたくて、情報を集めてるんだ」
「それはどうして?」
「好きな女性にそんな噂があってね」
「マジョーリカに入れ替えられた女性、ですか。おや、そういうことですか?」
「あなたは、俺を置いていくのが好きだな」
「いや!なんの、面白い。いえ、失礼。それでは、少し待っていただけますか?」
ヴィーナンテは悪戯めいて目を光らせた。手を叩いて付き人を呼び、客人をここに、と言付ける。ヴィーナンテは、楽しそうに笑っている。ライオットが不審な顔をして、ブラッドに目配せをするが、ブラッドは肩を竦めた。やがて間もなく、客人がやってきた。
「こ機嫌麗しゅう、ヴィーナンテ様」
ブラッドは崩れ落ちそうになった。
「って、え?」
「あ、え、エーデルワイス、君がなぜここに」
「え、ええと、その、ブラッド様こそ、どうして……」
前回二人が会ったときは告白の場面だった。それを思いだし、その結果を経て、二人の顔は赤くなったり、肩が落ちたり、目を伏せたりしたが、必死に何か言い出そうと、二人とも相手を気にして、見詰めあい、すぐ視線をそらし、だがそろりと視線を向け、そわそわしている様子をライオットは見詰め、そんなライオットにヴィーナンテが笑いかけた。
何か嫌な予感がした。
「エーデルワイス様はわたくしのスポンサーである、ハニーデッカー様の代理人として来てくれたのです。何故なら、エーデルワイス様はハニーデッカー様の婚約者だそうで。」
いやあ、すでにパートナーとして仕事を手伝われてるなんて、仲がよろしいですねえ、とヴィーナンテが言葉を続けた。
ブラッドは言葉を理解するのに時間を要し、押し黙って目を伏せてるエーデルワイスを見て、そしてライオットを見た。
ライオットは言う。
「大丈夫です、ブラッド様。略奪すればいいんですから」
ブラッドは少し途方にくれた気持ちになった。エーデルワイスのこと、自分はなにも知らなかったのかもしれない。
「……エーデルワイス、君さえよけれは少し話をしたいんだが、いいだろうか?」
エーデルワイスは弾かれたように顔を上げた。揺らいだ瞳が、しっかりとブラッドを捉えた。
「はい、是非」
「有り難う。ヴィーナンテ殿、客人をお借りするがいいだろうか?」
「ええ、どうぞ。となりの部屋をお使いください。窓際の扉から入れますよ。となりの部屋を使う者はわたくし以外おりませんので、ごゆっくり歓談されてください」
「私はここで、待っております」
ライオットがヴィーナンテに顔を向ける。ヴィーナンテがなにかしでかさないか見張ると本人に伝えているがヴィーナンテは気にしないようで、では、お酒でも、と言う。
ブラッドはエーデルワイスと共にとなりの部屋へ移動する。
ライオットは少し息を吸った。
「事態が好転するといいですねえ」
ヴィーナンテはまるで事態が悪化することを望んでいるようだったが、ライオットは怒りも威圧もしなかった。意味がないことは分かっていた。だから、代わりに言う。
「王を入れ替えたマジョーリカの話を聞こう。よく回る舌で、好きなだけ悪辣に語るがいい」
ヴィーナンテは微笑んだ。
例えこれから何が語られようとも、本当のことは、ヴィーナンテの美しさだけみたいだった。
令嬢転生もの~続き
「好きだってッ言われちゃったッ」
好きな人に好きって言われたのにッ!と泣きじゃくるエーデルワイスをアンジェラは慰める。
「お互い好きならいいじゃないのかしら」
「でもッ私はエーデルワイス様じゃないし!」
「だって、マジョちゃったんでしょう?」
「それは、でも、違うから」
アンジェラが、私、実はエーデルワイス様じゃないの、と言われたのは数ヵ月前のことだった。
アンジェラとエーデルワイスは仲が悪かった。性格や好みが不一致というより、エーデルワイスがいつも不機嫌で野犬みたいにいきり立っていたのだ。昔の彼女は主張をはっきりする子ではあったけれどどこかいつも楽しそうな子で、何をしですかわくわくするようなところがあった。だから、本当のところアンジェラとエーデルワイスは仲がよかったのだが、エーデルワイスの母親が病気で亡くなって再婚してから、だんだんエーデルワイスは変わってしまった。仕方ないことだったのかもしれない。けれど本当にそうだったのだろうか?
目の前で泣きじゃくる今のエーデルワイスみたいに、あの頃のエーデルワイスもアンジェラの前で泣いてくれたらよかったのに。
「マリ、ねえ、聞いて」
「う、うん」
「今のあなたがエーデルワイスなのよ。あなたが例え別の世界の、マリという人間であっても」
マリ。それがエーデルワイスと名乗る彼女の本当の名前だ。
マリは、戸惑う。
「私は、でも、エーデルワイス様の人生を奪ってしまったから。それは、許されないことだよ」
「あたしは今のエーデルワイスが好きよ」
マリは顔を伏せた。
本当にそう?と、マリは聞きたがってるようだった。尋ねられてもアンジェラには答えられないかもしれない。
彼女が好きな人の告白を受け入れられないのは当然かもしれない。
自分の好意ですら、アンジェラは不意に判断しかねる。これは、元のエーデルワイスに向けているものなのか、それとも、マリだからか。
マリは思い切り涙をぬぐった。豪快にハンカチで鼻を拭いて、真っ赤な目でにっこりと笑う。
「アンジェラ、有り難う」
手を握って、彼女が言う。
「私の秘密を抱えてくれて。私はエーデルワイス様にふさわしい人生を送ってみせるよ、あなたの良き友人でいられるように」
「……どうして?充分、あなたはあたしの友達だわ」
「有り難う。ーーねえ、課題はもうやった?メヌエット先生の文法が難しくて、わからないところがあるの」
「え?そうね、そこはジオーレの伝説の二部にある言いまわしを参照にしていて……」
あたしはこのままでいいのだろうか。アンジェラは、いつも通りに振る舞ってみせるエーデルワイス………マリをみて思う。
「……マリ。あなただって、好きに恋をしていいはずよ」
「いいの。そもそも、私の婚約者は決められているし」
「ーーそれこそ」
それこそ、エーデルワイスが望んだ人生なの?
アンジェラは、マリを見詰めた。彼女が思うように生きることがエーデルワイスに繋がる気がする。けれど、それは、彼女自身を軽んじることになりやしないだろうか?マリはあくまでもエーデルワイスの付属品なのだろうか。
「大丈夫、安心して。案外悪い人じゃないのよ、ハニーデッカー氏って」
「それは、分からないわよ。あの人、ほとんど喋らないんだもの」
「いい人なの。でも、人の間には言葉が必要なのが分からないみたい」
あからさまにアンジェラは顔をしかめる。そんな男の人、最悪じゃない?
「というか、ブラッドってあなたの婚約者のこと知ってるのかしら?」
「…………………………そういえば、婚約を前提として、と言われた気がする」
「マリって案外、秘密主義よね?」
「そ、そうかな。好きな人の前で婚約者の話はしたくないから………」
「んー。それもそうね。あたしもブラッドに言ってないものね」
「………アンジェラとブラッドさんって仲良しよね?」
「まあね。でも、全然恋とかはないから、安心して。あたしはむしろライオットの方がそういう意味で好きだもの」
「えぇっ!そうだったの?!」
「ライオットはブラッドラブだから、全然相手してくれないんだけれどね」
「いいな、ライオットさんは……ずっとブラッドさんと一緒にいられて」
「何言ってるのよ!マリはそのブラッドに好きって言われてるじゃないの!」
「うう、でも、それはぁ、ダメだから…………」
変なところでマリは頑固だ。こうと決めたらやり抜こうとする強さがあって、それがマリのいいところでもあるが、融通がきかないときがある。
アンジェラは、こっそりとため息を吐いた。再び泣きそうな顔をしながら、エーデルワイスの姿をしたマリという彼女は本とノートにかじりつく。
彼女は、エーデルワイスの日記を読んだことがあるらしい。そうして、彼女は決めたのだ。ーー医者になる、と。
それは、エーデルワイスの夢なんだと彼女は言っている。
じゃあ。それなら。マリの夢はなんなんだろう?あなたはどうしたいの。本当はどうしたいの?
アンジェラには二人が入れ替わって見えないときがある。エーデルワイスという人間とマリという人間と。そのどちらも、アンジェラにとっては、友達だった。本当はずっと、そうだった。でも、忘れてしまっていたことだ。マリというエーデルワイスは、アンジェラが求めていた彼女だった。
「マリ。あたしはあなたの友達よ」
マリが涙で腫らした目元で嬉しそうに笑う。アンジェラは、人知れず胸を痛めた。
令嬢転生もの~
「私はあなたの好きな人ではありません」
噴水が虹を作る。煌めきと、飛沫。周囲は手入れの行き届いた草木が二人を歓迎している。ひとつひとつの花が揺らめいて、優しく微笑んでいる。
ここは二人の思い出の場所だった。彼の方が二つ年下で、彼女の方が年上で、出会ったときはまだ幼くて、パーティーの催しに参加してみたけれど、よく分からなかった。互いに抜け出した先がこの噴水の場所で、二人は二人だけでしばし遊んだのだ。なんの会話をしたかまでは思い出せないけれど、いい印象を抱いたことを覚えている。その後、学園にて二人は再会したけれど、その時は彼女にいい印象を覚えなかった。野犬のような鋭さが彼女の眼差しにあったからで、ーー決して悪い印象ではない、だが、戸惑ったことを覚えている。彼女に何があったのだろう?
暫くして彼女が病気で伏せたという話を聞き、それから間もなく彼女に出会った。妙な言い方だ。彼と彼女はすでに出会っていた。けれど、その時彼は、ーー出会えた、と思ったのだ。
「いかがでしたか」
彼の従者であり友人が、声をかけるまで彼は噴水の前で立ち竦んでいた。
「そのご様子だと、振られましたか」
気遣うか揶揄するか、半分ずつの感情が入り交じった言葉を向けられ、彼は肩を竦めた。
「さて。嫌われているわけではないのだが」
「だが?」
「しかし、別の問題はあるようだ。ここで話すのも難がある。場所を移そう」
執務室へ移動し、人払いし、他の耳がないことを確認する。
ともあれ、従者の淹れてくれたお茶を飲み、彼は先ほど起きたことを話す。
彼女、ことエーデルワイス嬢に彼は告白をした。
「なんと」
「君が好きだから婚約を前提に気持ちを受け入れてくれないかと」
「あなたは王位継承者じゃありませんからね。縁談も断っているみたいですし」
「他者の目論見はさておいて、俺はこれでもいい家庭を築きたいと思っているんだ」
「まるでジェルボン卿のような?」
「そうだ。あのお方は愛人を作らないし妻子を大事にしている。仕事振りも見事だ。前の協会の問題についても見事な采配だった」
「彼はあなたの叔父でもありますしね。エーデルワイス嬢はなんと答えたんですか?」
「私はあなたの好きな人ではありません」
「あなたが前にアンジェラ嬢を好きだった話じゃないんですか」
「違う。第一アンジェラとは友人だ」
「他の御仁から見ると大層仲良しですよ」
「友人なのだからそうだろう」
「とはいえ、理由をお聞きになったのですか?」
「もちろん。だが、教えてはくれなかった、謝るばかりで」
「ははーん」
「何だ」
「ブラッド様振られましたね」
「振られてないだろう」
「おおむね振られてますよ」
「振られてないだろ」
「彼女嫌がってるじゃないですか、気の多い男だって」
「だからアンジェラとは………、わかった、ならもう一度告白してその上でアンジェラとは友人であることを説明してくる」
「一日に二度告白されるのは少しどうかと思いますよ」
「俺もそう思う」
「ーーそういえば」
「何だ」
「エーデルワイス嬢のことで噂を耳にしたことがあります」
従者の口ぶりからして、彼ことブラッドには従者がずっと黙っていたことだとわかった。従者はさもいま思い出したように言う。
「エーデルワイス嬢はマジョーリカによって取り替えられたのだと。だから、いまの彼女は善良なのだと。……もっともあくまでも噂なのですが」
マジョーリカとは、いたずら好きの妖精で、別の世界の人間とこちらの世界の人間を入れ換えては遊んでいる、という伝承を持つ。もっぱら真実とみな信じているわけではなく、噂話程度にマジョーリカのせいであの人は結婚して変わってしまったんだとか、マジョーリカに魅入られたから心変わりされたんだ、とかそのように迷信のように扱われている存在だ。だが、エーデルワイス嬢が病床に伏せって以降、がらりと変わったのは事実だった。
「わかった」
従者はよく知っている。わかった、と彼の主が言う時、大抵はわかってないのだ。
「俺がその噂の真相を突き止める。そしてーー」
「そして?」
「今度こそ告白を成功させるのだ!行くぞ、ライオット!」
どこに、と聞く前にブラッドが言う。
「まずは情報を集める。吟遊詩人や書庫などを調べるぞ。古くから書庫にいるガヘムならなにか知ってるかもしれないしな!」
この人、無駄に有能なんだよなとライオットは思う。主としての尊敬すべきところだが、一方でこういうところが火種になっていることも知っている。
ーー何か、妙なことにならなければいいが。
うっすらと抱く予感を横において、ライオットは自分の主人を追いかけた。
ブラッドの恋の行く末に幸あらんことを。
-Tags-
- ハッシュタグは見つかりませんでした。(または、まだ集計されていません。)
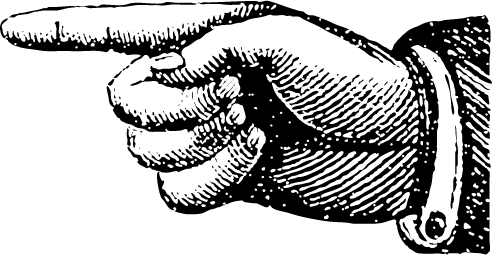





チャラ風犬